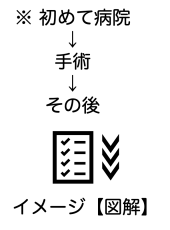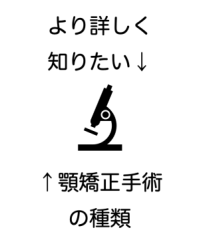顎変形症治療について
顎変形症とは
上顎骨ならびに下顎骨あるいはそれら両方の大きさや形態、位置などの異常や上下顎間関係の異常などによって、顎顔面の形態的異常と咬合の異常をきたし、美的不調和を示すものを言います。一般的には、下顎が前に伸びすぎていたり、顎が小さいなどの理由で、上下の歯のかみ合わせが大きくずれている場合などを指します。
症状としては、うまく咬めない、言葉が発しづらい、食べ物の消化が悪い、容貌に関して悩んでいる等があります。
この様な場合は、通常の矯正歯科治療のみでは、治療が困難なため、「矯正歯科治療」と「顎矯正手術」を組み合わせることで、良好な結果を得ることが可能になります。治療の目的は、そしゃく機能の回復、顎を含む顔面の形態的異常を修正することで、美容形成とは異なります。
適応症かどうか?
顎変形症と診断するためには、認定をうけた施設でX線検査や模型診察を行う必要があります。その上で、手術の適応か否かは、顎矯正治療を専門とする口腔外科医や矯正歯科医の診断が必要です。
治療は基本的には健康保険が適応されます。また顎矯正手術は高額療養費に対する償還払い制度の対象になりますので、1か月間に支払われた医療費の自己負担額(差額ベッド代などは除く)が定められた限度額(標準報酬月額により変わる)を超えた場合に、「患者様からの請求、申請」により払い戻される場合があります。該当するかどうかのご確認や申請の手続きは市町村の窓口などでお願い致します。
施設基準
術前矯正治療を保険で取り扱うためには、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長に届け出た保険医療機関(矯正歯科)である必要があります。当院では北海道大学歯科矯正学教室から、派遣医がきて診察を行っており、これに該当します。また、そしゃく筋筋電図、下顎運動検査、歯科矯正セファログラム、口腔内写真および予測模型などによる評価や分析が必要です。
矯正歯科治療前にしておくこと
術前矯正治療の前には、必要に応じて虫歯や歯周病の治療を終えておくことが必要です。また親知らずや小臼歯などの抜歯が必要になることが多くあります。さらに喘息や貧血などの全身的な病気がある場合は、安全に手術を行うために支障となる場合があることから、主治医の先生と協議し、必要に応じて治療が必要になる事があります。
術前矯正治療
手術の前には、上顎・下顎それぞれの位置と形態に応じた歯並びに改善するために、術前矯正治療(ブラケットやバンドを装着)を行い、術後に咬めるようにしておきます。歯が動きやすい方、動きにくい方がいらっしゃいますので、術前矯正治療に要する時間はあくまでも予測となりますが、通常は1年〜1年半程度を要します。
術前検査
最終的な手術の方法を決定するため、模型の型取り、X線・CT撮影、写真撮影等が必要です。また全身麻酔での手術を行うにあたり、安全に行うために術前検査も必要になります。検査は血液検査、尿検査、胸部X線写真、心電図検査などです。また術式により、自己血の貯血を行う場合があります。その際は、手術日の数週前から、自己血を採取、保存しておきます。
入院・手術
手術の2日前に入院します。入院後は、手術中・後に使用するシーネ(歯型 から作られた樹脂製の薄いプレート)の調整や、麻酔科受診などがあります。手術は全身麻酔下に、ほとんどの場合は口腔内から行います。手術後の食事は、翌日から流動食から開始し、徐々に形態のあるものに変更していきます。傷の安静を図り、かみ合わせをしっかりさせる目的で、シーネと顎間ゴムを使用します。その後、かみ合わせがずれないように、また口が開くようにリハビリを開始します。傷が落ち着く術後10日間前後で抜糸を行います。
術後矯正治療
術後は、約1ヶ月程度で骨が安定し、3ヶ月程度でしっかりとつきます。個人差がありますが、かみ合わせが安定し、口がしっかりと開くようになった術後1〜2ヶ月前後から、術後矯正治療を開始します。手術によりかみ合わせは、良くなっていますが、歯の感覚は鋭敏なため、この治療により微調整を行い、しっかりと安定したかみ合わせにしていきます。
チタンプレート除去
骨の固定は、一部に吸収性プレートを使用することがあり、その場合は除去は不要ですが、大部分はチタンプレートを使用しています。感染や破折などがない限り、除去しなくても問題ありませんが、将来インプラントや義歯を作製する場合や、頭や首の病気でCTやMRI撮影を行う際に、ハレーションと言って、画像が乱れる原因となることがあります。そのような場合や、除去の希望がある際は、全身麻酔下に除去を行います。短期間の入院ですが、全身麻酔下での手術になります。
経過観察
術後は、退院後約1ヶ月間は、10日前後に1回の受診が必要となります。
その後は、術後3ヶ月、術後6ヶ月で受診して、かみ合わせに問題がないか、骨がしっかりとついたか等を、画像検査で確認します。